製図は工業製品との関係が深いので、国内では日本工業規格(JIS)、国際間では国際標準化機構(ISO)で細かく規定されている。
日本工業規格(JIS:Japan Industrial standard)は、工業全般に必要な標準化と技術の発展を図るために1949(昭和24)年工業標準化法が公布されたことによってスタートした。続いてこれに基づいたJIS Z 8302(製図通則)が製図に関する共通事項を規定したものとして1952(昭和27)年9月に制定されている。
その後、幅広く定められているJISの中で製図は、不足部分を補いながら基本及び一般事項に関してまとめられた「製図総則(JIS Z 8310)」をはじめ、さまざまな規格が定められて(日本規格協会*によって運営されて)いる。
共有する情報という特徴から見れば、製図も記号を利用したコミュニケーション(communicaton)の1つであり、元々コミュニケーションは、共通性(common)をベースとして成立するものである。製図では共通性を厳密な規格に求めている。
製図法による分類だけでなく、建築・土木・電気など「領域で分類されるもの」は、表示方法や記号類の扱い方などに独特の表記法に特徴があり、機械製図に対して建築製図、土木製図などと呼ぶ。
更に近年国際化が進んできている。JISも国内だけに対応するのではなく、国際標準化機構(ISO)*に対応するように改正が行われ、より一層の標準化が進められている。
その後、幅広く定められているJISの中で製図は、不足部分を補いながら基本及び一般事項に関してまとめられた「製図総則(JIS Z 8310)」をはじめ、さまざまな規格が定められて(日本規格協会*によって運営されて)いる。
共有する情報という特徴から見れば、製図も記号を利用したコミュニケーション(communicaton)の1つであり、元々コミュニケーションは、共通性(common)をベースとして成立するものである。製図では共通性を厳密な規格に求めている。
製図法による分類だけでなく、建築・土木・電気など「領域で分類されるもの」は、表示方法や記号類の扱い方などに独特の表記法に特徴があり、機械製図に対して建築製図、土木製図などと呼ぶ。
更に近年国際化が進んできている。JISも国内だけに対応するのではなく、国際標準化機構(ISO)*に対応するように改正が行われ、より一層の標準化が進められている。
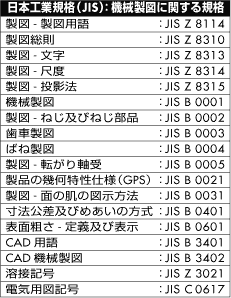
などがある。
|
JIS部門別一覧
|
||
|
JIS
|
A
|
土木及び建築 |
|
JIS
|
B
|
一般機械 |
|
JIS
|
C
|
電子機器及び電気機械 |
|
JIS
|
D
|
自動車 |
|
JIS
|
E
|
鉄道 |
|
JIS
|
F
|
船舶 |
|
JIS
|
G
|
鉄鋼 |
|
JIS
|
H
|
非鉄金属 |
|
JIS
|
K
|
化学 |
|
JIS
|
L
|
繊維 |
|
JIS
|
M
|
鉱山 |
|
JIS
|
P
|
パルプ及び紙 |
|
JIS
|
Q
|
管理システム |
|
JIS
|
R
|
窯業 |
|
JIS
|
S
|
日用品 |
|
JIS
|
T
|
医療安全用具 |
|
JIS
|
W
|
航空 |
|
JIS
|
X
|
情報処理 |
|
JIS
|
Z
|
その他 |
| 国際標準化機構 (ISO:International Organization for Standerd): 1835年のメートル条約を起源とし、国際電気標準会議、万国規格統一協会を経て、1947年、ジュネーブに設立された。 国際的な標準規格を策定することにより、世界規模で流通する知識・技術・商品が消費者や企業間取引において、信頼性を担保する大きな役割を果たしている。現在、世界約146ヶ国で60万以上の団体が認証取得。 同機構が策定する標準化規格の総称としても用いられる。 |
| 日本規格協会: 大日本航空技術協会と日本能率協会の各規格担当部門が合併して昭和20年12月6日商工大臣の認可を受けて設立された。“工業標準化及び規格統一に関する普及並びに啓発等を図り、技術の向上、生産の能率化に貢献すること”を目的とする。 財団法人日本規格協会: http://www.webstore.jsa.or.jp/ |