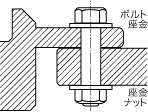ただし、効率よい作業のためには、作図する人がどこまで対象とする図形を立体的に把握できているかが一番大切である。、
基本的には対象とする形状の“最も特徴的な面方向”を正面にすると、図面を受け取った人も読み取りやすくなり、自分も描き易くもなる。そこでこれを主投影図として“位付け”する。
右図のように主投影図だけで製図を完了できるものもあるので、「正面の選択」は投影図法では一番のポイントになる。
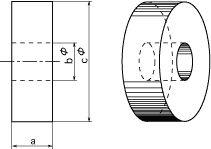
図例:
右に示す形状は、左の図だけであらわすことができる(補助記号「Φ」で直径を示す=円形)ので、補足投影図は必要ない。
右に示す形状は、左の図だけであらわすことができる(補助記号「Φ」で直径を示す=円形)ので、補足投影図は必要ない。
また作図する内容から投影面だけでなく、補助投影図をどう利用するかなど、読み取る人のことも考えて、どう描くか?柔軟な対応が必要になる。
補助投影図にも、次のような目的と用途によって種類がある。
●部分投影図(partial view):
部分的に補助すれば済む場合、その部分だけを図面内に描き入れ、補助する。
●局部投影図(local view)
より部分的、局部的な補助投影図をいう。主・補足投影図から中心線や引き出し線などを使って関係を表示しなければならない。
●回転投影図(revolved projection)
傾きがある部品では、正投影では寸法の読み取りなどで実寸法が表示できない場合が多く、読み取りに手間取ったり、間違いを起こしやすくなる場合もある。
そこで、実寸を表示するために回転して直角に直して、実形を表すことが認められている。そのための表示方法。
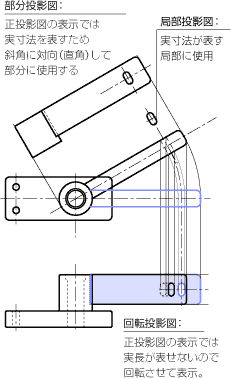
右図ではどちらも正面図と側面図で表されているが、上と下では正面の前後、側面図の方向が逆になっている。
上がかくれ線だらけになってしまうのに対して、下の図では断面図も加えて加工に対しての配慮を考えている。
かくれ線では形状が判断しづらいので、断面図なども利用して、より具体的に形状を表現するようにするほうがよい。
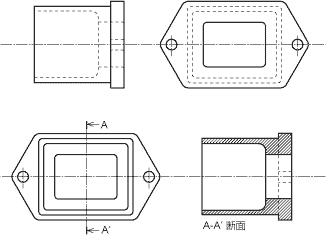
- 全断面:全体を切断する
- 半・片、部分、局部断面:必要な部分だけを切断する
- 斜角断面:相交する2つの平面で切断する
- 階段状(オフセット)断面:2つ以上の平面で切断する
- 曲面断面:曲がった管などの中心線に沿った断面で表示する
他にも複合断面、薄物断面などがある。
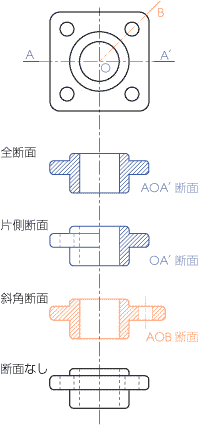
右図の「斜角断面」では切断線を途中で45°回転させ(折り曲げ)て平面図で示し、正面図で同じ投影図内に表示している。
切断線(平面図)の位置または延長線上に断面図(正面図)を描く。
右上図中、平面図上にAOA'断面とAOB断面が表示し、正面図にはどの断面なのかを必ず明記すること。
右図のように全体の外形図を正面図とするなら、断面は側面図になり、右側に描くのがルールだが読み取りづらい。そこで断面を正面図の下に合成した方が解りやすい。
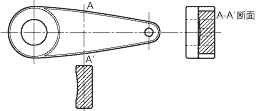
組み立て図のように部品がたくさんある場合には、切断すると返って分かりにくくなるもののある。
原則的にボルト・ナットやワッシャ、小ネジ、リベット、各種ピン類などは長手方向に断面を取らずに描画する。